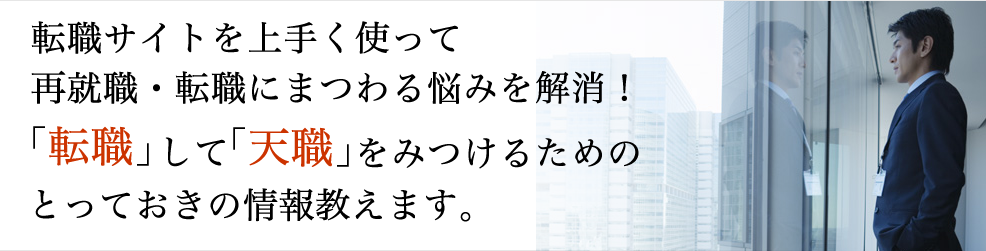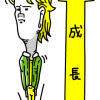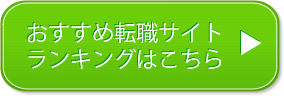
失業保険受給までの流れ
失業保険を受給するにあたり、いろいろな手続きが必要になったり、実際に支給されるまでに少し時間がかかったりするので、前もって受給までの流れを把握しておくと無駄にイライラしたりしなくていいでしょう。
①離職票の受け取り
まず、離職後、勤めていた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。
離職票というやつですね。
それから、会社がハローワークに「離職証明書」というものを提出しますが、それは離職前に本人が記名押印あるいは自筆による署名をすることになっているので、その時に離職理由等の記載されている内容についてしっかりと確認しておいてください。離職理由に記載ミスがあると、受給資格が変わってしまうこともあり得ますので。
また、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合などは管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
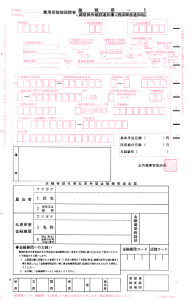
②受給資格の決定
管轄のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行ってから離職票を提出します。
一緒に必要な書類は以下のとおりです。
「雇用保険被保険者離職票」
「雇用保険被保険者証」
「本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、住民基本台帳など)」
「写真(縦3cm x 横2.5cmの正面上半身のもの)2枚」
「印鑑(認印可)」
「本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)」
ハローワークは、受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定を行います。このとき離職理由についても判定しますが、簡単な聞き取りをされることがあります。
受給資格の決定後、受給説明会の日時を確認したら、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
③雇用保険受給者初回説明会
指定されている日時に開催されますので、必ず出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。説明をしっかり聞き、制度について十分理解するようにしてください。
その後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を渡され、第一回目の「失業認定日」の通達があります。
④失業の認定
原則的に、4週間に一度、失業の認定(失業状態にあることの確認)してもらうために、指定された日時にハローワークに行き、「失業認定申告書」にどのぐらい求職活動したのかなどの状況を記入して、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
ここで大切なのは、「失業状態」とはどういう状態か、ということです。
「失業とは、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ということです。
なので、以下のような状態のときは失業保険を受給できません。
・病気やケガの為に、すぐには就職できないとき
・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することが出来ないとき
支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由などによっては、待機期間満了後3ヶ月間は支給されませんが、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
実際は求職活動をしなかったにもかかわらず、活動をしたかのような虚偽の申告をしたり、就職やパート、アルバイト、又は自営の開業などをしたにもかかわらず、そのことを申告しなった場合や、収入を隠したり偽った申告をした場合は「不正受給」となり、それ以後の支給がすべて停止され厳しい処分が行われますので、そのようなことは絶対にしないようにしてください。
⑤受給
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間となっています。ご注意ください。
さらに、付け加えておくと、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない「待機期間」というものがあり、また、正当な理由が無く本人の都合で退職した場合や、本人の責任による重大な理由により懲戒解雇された場合は3ヶ月の給付制限があります。
このように、実際に受給を受けるまでには少し時間がかかってしまうので、離職後はなるべく早めにハローワークで手続きをしてしまうのがいいでしょう。
この制度はあくまでも「求職支援」のためのものですので、失業認定期間中は積極的に前向きに求職活動を行ってくださいね。
関連記事
-

-
失業保険の受給資格について
失業保険は、失業中の人の生活の心配を少なくし、安心して仕事探しができるありがたい支援制度ですが、失業
- PREV
- 失業保険の受給資格について
- NEXT
- 退職後の健康保険の手続き